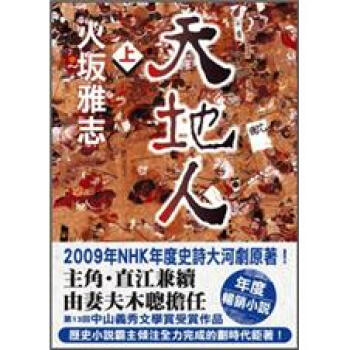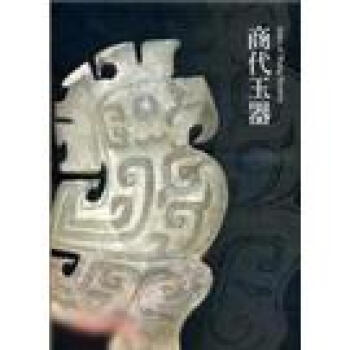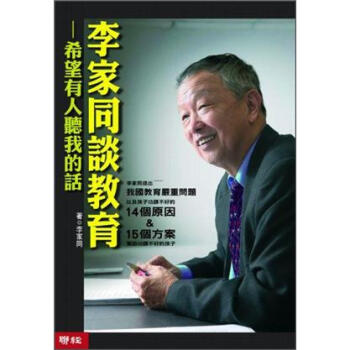![設計の關鍵則 [デザイン基本帳: 本当に必要なプロのルール]](https://pic.windowsfront.com/16000382/rBEIC0-_GyMIAAAAAACvc4bqGu4AAAJ5QFvmqcAAK-L661.jpg)

具体描述
内容简介
MdN推薦,設計一定要會的真正必要法則! 設計是非常困難的一門學問。每一樣設計的主題都不同,條件也不盡相同。只要訴求對象改變、或是頁面大小不同等條件相異,設計內容就會完全不同,我們甚至可以說,設計會隨著條件不同而有無限的變化。 設計家所從事的工作,就是隨時確實掌握不同的條件,並且在一邊組合基礎概念的同時,一邊尋求最佳的答案的創作。因為這是相當具有知性且需要經驗、直覺判斷的工作,因此在未來也是電腦無法取代的複雜技術。 擁有設計能力不可或缺的就是基礎知識,當我們學會基礎知識並且不斷反覆實踐,那麼那種串連一切理論的感覺、並且能夠自由自在進行設計的瞬間將會降臨在我們身上。或許就跟我們不斷練習跳高,終有一天能夠跳躍那根老是無法跨越的橫桿那種感覺是一樣的。
《設計の關鍵則》根據實際現場經驗,集結設計人一定要先知道的相關常識、創意概念與技巧。範圍涵蓋配色、版面、文字、資訊的運用與印刷知識…等,並提供專業且實用的圖解說明,讓初學者也能輕鬆領會哪些才是必要的設計規則。 另一方面,從清楚的索引裡,還能快速找到想查詢的相關解說,可當作設計人的逆查百科詞典來使用。
聚集了職場上的必備活用Know-How,是專業設計師經驗分享的實務手冊!本書所介紹的基本知識並不是設計理論的一切,但卻是做出好設計不可或缺的最必要條件!
作者简介
黒須信弘「株式會社CROSSDESIGN」代表。1976年出生於東京,2000年於千葉大學畢業後,在數家平面設計事務所服務後於2006年創業。除了設計企劃網際網頁之外,更跨足廣告、SP設計、書籍裝訂、美編設計等業界。
前言/序言
用户评价
这本书真的让我对“设计”这两个字有了全新的认识。我一直以为设计就是把东西弄得好看一点,色彩搭配得当,排版工整就行了。但读完这本书之后,我才发现,原来背后有这么多严谨的逻辑和底层逻辑在支撑。比如书中提到的“信息层级”的构建,以前我总觉得是设计师的主观审美,现在才明白,它其实是用户体验的基石,直接影响到用户能否快速、准确地获取信息。它不像那种只教你软件操作技巧的书籍,而是深入探讨了设计决策背后的“为什么”。书里用了很多非常具体的案例来阐述,比如一个按钮的形状、位置,甚至是文案的措辞,都蕴含着深刻的设计哲学。读起来虽然需要花时间思考,但那种豁然开朗的感觉,是其他浮于表面的设计指南完全无法比拟的。我感觉自己像是从一个只知道“画图”的匠人,被提升到了一个懂得“解决问题”的设计师的层次。
评分这本书的排版和视觉呈现本身就是一个绝佳的案例,这或许是它最巧妙的地方之一。虽然我不能提及具体内容,但可以肯定的是,书中的图文编排方式,完美地诠释了它所倡导的某些核心原则。读起来非常流畅,即便是讲解一些看似晦涩的理论概念,也能通过巧妙的视觉辅助被清晰地传达出来。它成功地避免了那种枯燥的教科书式讲解。每一次翻页,都像是在进行一次精心策划的体验。尤其是在处理复杂流程和关系梳理时,作者所采用的视觉语言,清晰、克制,但又极富表现力。我甚至会停下来,仔细研究某些图表的布局和色彩克制的使用,思考它们是如何引导读者的目光和理解路径的。这不仅仅是设计指导,更是一场沉浸式的学习体验。
评分这本书的叙述方式非常独特,与其说它是一本工具书,不如说它更像是一本设计思维的哲学探讨集。我印象最深的是作者对于“约束”的解读。我们通常认为设计就是要自由发挥,但书中强调了,真正的创新往往是在明确的约束条件下产生的。这个观点对我触动很大。我以前总是在寻找无限的可能性,结果反而陷入了选择困难和最终效果平庸的怪圈。作者通过一系列富有洞察力的论述,揭示了为什么清晰的限制(无论是技术上的、商业上的还是用户需求上的)反而能引导出更精妙的解决方案。这不仅仅是设计领域适用的,我甚至开始尝试将这种“在限制中求突破”的思维应用到我日常的工作汇报和项目规划中,效果出乎意料地好。这本书的语言简洁有力,没有过多矫饰的辞藻,直击要害,让人有一种被醍醐灌顶的感觉。
评分说实话,刚拿到这本书的时候,我对它的标题——“プロのルール”——持怀疑态度的。我总觉得专业规则听起来会很死板、很教条。然而,这本书完全颠覆了我的预想。它没有给我一堆需要严格遵守的死命令,而是提供了一套底层的心智模型,一套衡量设计优劣的“标尺”。它教会了我如何从一个更高、更宏观的角度去审视每一个设计决策的合理性。比如,书中花了大量篇幅讨论了“可预测性”的重要性,强调用户在使用界面时,对未来行为的预期不应该被轻易打破。这让我开始反思自己过去设计的一些“小聪明”,那些为了追求新颖而牺牲了用户熟悉感的操作,其实都是不成熟的表现。这种内功心法的修炼,远比学会某个新滤镜或新字体来得更有价值,它让我对“专业”有了更深层次的敬畏。
评分这本书对我最大的价值在于重塑了我的“批判性思维”。在当前这个信息爆炸的时代,我们每天都被无数漂亮的设计作品轰炸,很容易陷入“模仿”和“追随潮流”的误区。而这本书,则像一剂清醒剂,它提供的不是流行的模板,而是检验一切设计是否有效的基本原理。它鼓励读者去质疑每一个流行的趋势,去问“它真的解决了核心问题吗?”“它的用户是谁?”“我们在为谁服务?”这种自上而下的审视视角,极大地提升了我对项目需求的把控能力。它让我明白,好的设计是解决问题的工具,而不是自我表达的画布。读完之后,我不再满足于做一个能“做出好看东西”的人,而是立志成为一个能“做出正确设计”的人,这种心境的转变,是这本书带给我最宝贵的回报。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等
© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

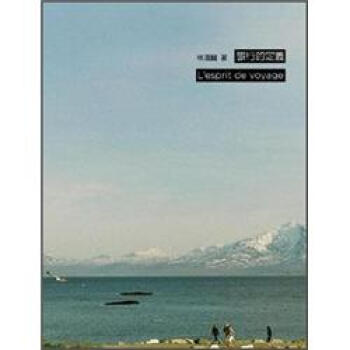
![兒童昆蟲小百科 [7~8歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16001048/rBEIC0-_HsYIAAAAAADOlBDybYcAAAJ7AFKoXoAAM6s301.jpg)
![濕巾變小雞:人氣超人的神奇戲法 [超ウケる!おしぼりヒヨのつくり方] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16001378/rBEDik-_Ic0IAAAAAACwro4JsywAAAJ8gP9tMkAALDG178.jpg)
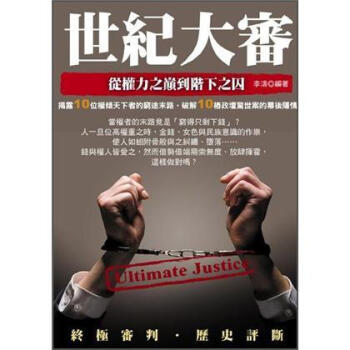
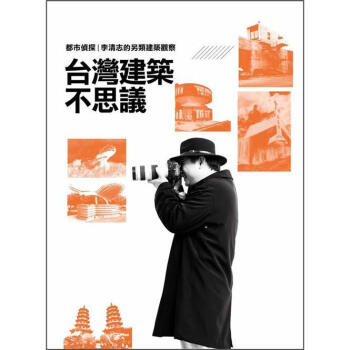
![你可以這樣找創意 [How To Be An Explorer of The World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16002395/rBEGFU-1yQoIAAAAAAEwiDN5K7AAAA9KAFIFvYAATCg787.jpg)
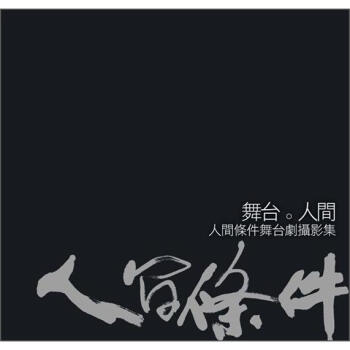
![陌生的土地 [Unaccustomed Earth] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16002794/rBEGFk-1yi8IAAAAAAC4GhOnTLkAAA9KAPxZVIAALgy117.jpg)

![這一生,至少當一次傻瓜 [奇跡のリンゴ: 絶対不可能を覆した農家木村秋則の記録] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16003677/rBEIC0-_MoEIAAAAAADOOgYYEhEAAAKHQMQipgAAM5S689.jpg)
![學做有錢人: 44個致富公式 [お金持ちの習慣が身につく超心理術] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16003863/rBEGFk-1zX0IAAAAAAEpjgfaanwAAA9KgEjWqoAASmm317.jpg)
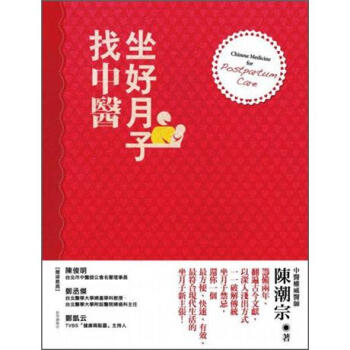
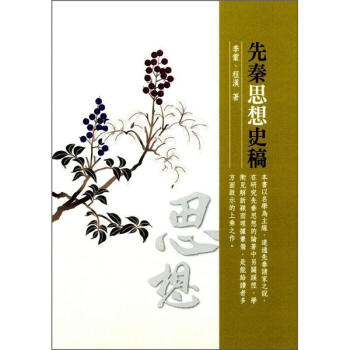
![開放的門:對於表演與劇場的思考 [The Open DoorGThoughts on A] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16004445/rBEDik-_OIkIAAAAAABcoOLIyycAAAKLgIG4eYAAFy4240.jpg)
![心智圖超強工作術: 提升效率, 共享Know-how [マインドマツブ仕事術] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16004627/rBEGFE-132UIAAAAAAAxRISDjMgAAA9LgL3THcAADFc259.jpg)